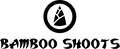【台高山脈ハンモック縦走】日本でいちばん山深いところ〈前編〉
こんにちは、BAMBOO SHOOTSスタッフの坂本です。
今回は5日間ハンモック泊で紀伊半島の奥地を縦走してきました。山行の様子と使用したギアのレビューを交えつつ、前編/後編に分けてお届けします。よろしければ最後までご覧ください。
歩いた舞台は台高山脈。高見山から大台ヶ原まで、奈良県と三重県の県境をなし”近畿の屋根”と称される1500m級の長大な山脈。大台ヶ原は国内屈指の多雨地帯でトウヒ林の南限、ニホンオオカミが最期までいた森、そして明治初期に実利行者が入山するまで、修験者さえ立ち入らない魔境として畏れられていた。現代ではドライブウェイが走り観光地然とした印象ですが、大台以北の山々はアクセスし辛く、今でも手付かずの自然が残り人を寄せ付けない雰囲気がある。日本でいちばん山深い場所の一つだと言えます。
アルプスや東北の稜線歩きも、北海道や九州の火山も、海辺のトレイルも大好きですが、人のいない深い森を一人で歩くのが私は何よりも好き。大峯奥駈道から台高の山並みを眺めた時に心奪われ、いつか歩きたいと想い続けている場所でした。

歩いたルートの概観は上図の黄緑の線(スーパー地形より引用)高見山地+台高山脈+尾鷲道、これらを繋げると登山道だけで100kmとなり、大峰山脈と並んで西日本最長クラスの縦走路となります。Y○MAPやヤ○レコに通しで歩いた記録はありませんが、高見山地や台高山脈の縦走記録はそれぞれあるので、どうやら一本の線で繋げられるらしい。
問題は大台ヶ原一帯がテント泊禁止となっている点。そもそも大台ヶ原という山はなく最高峰は日出ヶ岳、大台ヶ原一帯という漠然な範囲について、明確にどのエリアがテント泊禁止なのか管轄する部署へ確認をすると、吉野熊野国立公園の特別保護地区内が該当するとのこと。なのでエリア外で野営するよう計画し、4泊5日の行程となりました。

ザックはHMGの『CONTOUR35』を選びパッキング。幕はタイトルにもある通りハンモックとタープ。100kmのルート上全てが樹林帯なので、ハンモックが最も張る場所を選ばず自由に寝れるだろうと考えました。食事はクスクスとスパイスと自分で採って乾燥させたきのこ類を混ぜた物を湯戻し。食料まで軽さにこだわったものの、予備含め6日分の食料はさすがに嵩みます。ベースウェイトを3kg台に抑えても、カメラと食料と水3L全てを詰めてパックウェイト11kgでした。
<1日目>

 夜行バスで松坂駅に降り立ち、そこから路線バスを乗り継いで登山口へ向かいました。局ヶ岳が今回の縦走の起点であり、高見山地の西端、眺望が良く人気な里山のようです。登山口の神社はドウダンツツジと桜が見事で素晴らしい雰囲気、ここから沢沿いの旧登山道へ進み山頂まで一気に上がる。夜行バス移動直後の身体に急登が堪えます…
夜行バスで松坂駅に降り立ち、そこから路線バスを乗り継いで登山口へ向かいました。局ヶ岳が今回の縦走の起点であり、高見山地の西端、眺望が良く人気な里山のようです。登山口の神社はドウダンツツジと桜が見事で素晴らしい雰囲気、ここから沢沿いの旧登山道へ進み山頂まで一気に上がる。夜行バス移動直後の身体に急登が堪えます… 沢山の蜂たちに歓迎される無人の頂、山頂標識が立派です。CONTOURはさすがの背負い心地で、食料と水がMAXの状態でもまだまだ余裕がある。ボトムとショルダーポケット付きで防水で400g台は改めて隙のないザックだな~と思います。背面パットがないので背中側へ4つ折りにした山と道『Minimalist Pad』を入れています。MinimalistPadはハンモックで寝る時の掛け布団として、タープだけで寝る場合はスリーピングパッドとして兼用。
沢山の蜂たちに歓迎される無人の頂、山頂標識が立派です。CONTOURはさすがの背負い心地で、食料と水がMAXの状態でもまだまだ余裕がある。ボトムとショルダーポケット付きで防水で400g台は改めて隙のないザックだな~と思います。背面パットがないので背中側へ4つ折りにした山と道『Minimalist Pad』を入れています。MinimalistPadはハンモックで寝る時の掛け布団として、タープだけで寝る場合はスリーピングパッドとして兼用。
局ヶ岳は高見山地の好展望地、奥には台高山脈も見えています。因みに「局」と名のつく山は全国にこの”局ヶ岳”と志摩の”局ヶ頂”の2座だけらしい。偶然にも今年2月に熊野脇道と落人伝説が残る局ヶ頂を繋げて歩いたので、図らずも局を冠する山を制覇しました。

登山口付近はタラの芽やコシアブラが出ていて採りたい気持ちを抑えながら登り始めるも、標高1000m以上はまだ芽吹き前で光が良く入る明るい森。その中で一足早く咲き誇るアカヤシオが目を楽しませてくれました。
 局ヶ岳から先の稜線は、地形図に徒歩道の記号はなく一気に踏み跡が薄くなる。幸いにも標識が小まめに設置され、尾根も細いので道を外すことはなかった。高見山地は細かいアップダウンが多くて登り返しにうんざりしてしまうけど、土壌の水分含有量が多い鞍部ではバイケイソウの群生が迎えてくれてここでもまた癒される。
局ヶ岳から先の稜線は、地形図に徒歩道の記号はなく一気に踏み跡が薄くなる。幸いにも標識が小まめに設置され、尾根も細いので道を外すことはなかった。高見山地は細かいアップダウンが多くて登り返しにうんざりしてしまうけど、土壌の水分含有量が多い鞍部ではバイケイソウの群生が迎えてくれてここでもまた癒される。

 局ヶ岳から先の稜線は、地形図に徒歩道の記号はなく一気に踏み跡が薄くなる。幸いにも標識が小まめに設置され、尾根も細いので道を外すことはなかった。高見山地は細かいアップダウンが多くて登り返しにうんざりしてしまうけど、土壌の水分含有量が多い鞍部ではバイケイソウの群生が迎えてくれてここでもまた癒される。
局ヶ岳から先の稜線は、地形図に徒歩道の記号はなく一気に踏み跡が薄くなる。幸いにも標識が小まめに設置され、尾根も細いので道を外すことはなかった。高見山地は細かいアップダウンが多くて登り返しにうんざりしてしまうけど、土壌の水分含有量が多い鞍部ではバイケイソウの群生が迎えてくれてここでもまた癒される。
 春山の風が心地よくハンモックを張って暫し休憩、寝不足が祟ってつい深い眠りへ落ちてしまいそうに…。地面の傾斜も虫も気にせずサッと横になれるのがハンモックの良さで、夜寝るだけでは勿体無いですよね。
春山の風が心地よくハンモックを張って暫し休憩、寝不足が祟ってつい深い眠りへ落ちてしまいそうに…。地面の傾斜も虫も気にせずサッと横になれるのがハンモックの良さで、夜寝るだけでは勿体無いですよね。少し歩いた先で振り返る局ヶ岳、端正な山容で美しいです。
 暗い杉の植林と対極的な明るいヒメシャラの自然林、この時はそんな美林に和んでいたけれど、後々執拗な幼木のブッシュにヒメシャラを疎ましく思うことになるとは…
暗い杉の植林と対極的な明るいヒメシャラの自然林、この時はそんな美林に和んでいたけれど、後々執拗な幼木のブッシュにヒメシャラを疎ましく思うことになるとは…


 暗い杉の植林と対極的な明るいヒメシャラの自然林、この時はそんな美林に和んでいたけれど、後々執拗な幼木のブッシュにヒメシャラを疎ましく思うことになるとは…
暗い杉の植林と対極的な明るいヒメシャラの自然林、この時はそんな美林に和んでいたけれど、後々執拗な幼木のブッシュにヒメシャラを疎ましく思うことになるとは…
火器は久しぶりにガスストーブ。食事の湯戻し用、夜にまったり飲むお茶用、朝のコーヒー用と5日間で10回以上湯沸かしすることを考えると、燃料の効率からしてアルコールストーブの重量面での優位性が低くなります。湯沸かし回数が多いほどガスの手軽さや沸騰の速さの恩恵も際立ってきますし。湯戻し系の食事はジップロックに入れそこへお湯を注ぎ、空いたクッカーにセットして食べるとクッカーも汚れずコジーも必要ありません。TOAKS付属のメッシュサックは適度なクッションで保温性と断熱性があり、コジー的な使い方ができます。

5日間最も冷え込んだ朝で5℃くらい。シュラフは-1℃対応のENLIGHTENED EQUIPMENT『REVELATION SLEEPING QUILT 30°F』をハンモックのアンダーキルトとして使用し、綿物のジャケットがなくても暖かく眠れた。キルトの隙間風が寒い時は凌『カルフワタオル』で足元の絞り部分を塞いでドラフトカラー代わりに、『Minimalist Pad』を掛け布団にして対応しました。ダウンや化繊のジャケットがあれば0℃付近でもいけそうです。
タープはTRAIL BUM『CTタープ』280cm×200cmはハンモック泊やタープ泊で風雨を凌げる最小限のサイズ。四国遍路を共に歩いた思い入れの強い道具で、四辺のコードを抜いて軽くしています。ハンモックはENO『SUB6』ULハンモックの大定番。今まで1~2泊の山行や釣行でのハンモック泊経験しかなく、長めの縦走で使うのは今回が初めてです。ツリーストラップ&ウーピースリングは自作したもので、市販品には見当たらない30cm⇄200cmの調整幅で1ペア70gの軽さ。ハンモック泊とタープ泊の両方に対応できるシステムはどこでも寝る場を確保でき、その自由さは日没過ぎまでソロで歩く際の精神的な余裕となってくれました。ペグとライン込みの野営システム全体で500g。
<2日目>



初日は局ヶ岳から高見山地の中間まで進み、2日目は高見山へ向かって歩く。ピラミダルなピークが木々の間からもよく目立ちます。南側には奥香肌の山並みが広がっている。
 崩落地横をヒヤヒヤしながら通って山頂へ進み、台高の”高”の頂を踏み締める。ここで高見山地が終わり、ここからは台高山脈。台高は神武東征のルートだったのではという説や、高見山から大和を見渡したという伝承も残っています。山頂の高角神社には神武天皇を大和へ導いた八咫烏が祀られています。
崩落地横をヒヤヒヤしながら通って山頂へ進み、台高の”高”の頂を踏み締める。ここで高見山地が終わり、ここからは台高山脈。台高は神武東征のルートだったのではという説や、高見山から大和を見渡したという伝承も残っています。山頂の高角神社には神武天皇を大和へ導いた八咫烏が祀られています。


 崩落地横をヒヤヒヤしながら通って山頂へ進み、台高の”高”の頂を踏み締める。ここで高見山地が終わり、ここからは台高山脈。台高は神武東征のルートだったのではという説や、高見山から大和を見渡したという伝承も残っています。山頂の高角神社には神武天皇を大和へ導いた八咫烏が祀られています。
崩落地横をヒヤヒヤしながら通って山頂へ進み、台高の”高”の頂を踏み締める。ここで高見山地が終わり、ここからは台高山脈。台高は神武東征のルートだったのではという説や、高見山から大和を見渡したという伝承も残っています。山頂の高角神社には神武天皇を大和へ導いた八咫烏が祀られています。

高見山より見渡す台高山脈。裾野が広くて巨大で複雑な山塊は、一体どこが主稜線なのか今一つ掴めません。ここから進む台高山脈は、これまで歩いた高見山地と比べて一層人が入らず踏み跡が薄く、携帯の電波も殆ど入らなくなる。結果的に大台ヶ原まで人と会うことはありませんでした。
電波がある内に最新の天気予報をチェックして美しい広葉樹林を降って行く。





縦走路の序盤は標識があるものの、全体を通してかなり少なく僅かなピンクテープを頼りに進むようになります。
どの方角を見ても人工物がなくて遥か果てまで山並みが続いているだけ、歩きながら深山へ分け入る感慨に耽る。
 樹林帯から急に開ける草原は、鹿たちと登山者の楽園、明神平。元々はゲレンデだったみたいですが、今や近畿を代表する山のテント場。ここでタープ泊する予定でしたが、絶妙に早く着いてしまい水だけ補給して先へ進むことに。明神平でタープ泊、開放感あって最高だろうな…またいつかゆるめの山行で来ようと静かに誓いました。
樹林帯から急に開ける草原は、鹿たちと登山者の楽園、明神平。元々はゲレンデだったみたいですが、今や近畿を代表する山のテント場。ここでタープ泊する予定でしたが、絶妙に早く着いてしまい水だけ補給して先へ進むことに。明神平でタープ泊、開放感あって最高だろうな…またいつかゆるめの山行で来ようと静かに誓いました。 今年は近畿も雪が多かったのか、標高1300m以上の北斜面には所々残雪がありました。ブナの根本は一律に曲がっていて、この木々がまだ細かった時代はさぞ雪が多かったことが伺える。半世紀前の紀伊半島では場所によって一晩で胸の高さまで雪が積もることも珍しくなかったらしい、今では考えられませんね。
今年は近畿も雪が多かったのか、標高1300m以上の北斜面には所々残雪がありました。ブナの根本は一律に曲がっていて、この木々がまだ細かった時代はさぞ雪が多かったことが伺える。半世紀前の紀伊半島では場所によって一晩で胸の高さまで雪が積もることも珍しくなかったらしい、今では考えられませんね。
 この日は暗くなる前に行動を終え、お茶を沸かしてダラダラタイム。チェックした天気予報では降水確率0%で風も弱い、ならばタープは張らずにキルトだけ。設営も撤収も3分以内に終わります。
この日は暗くなる前に行動を終え、お茶を沸かしてダラダラタイム。チェックした天気予報では降水確率0%で風も弱い、ならばタープは張らずにキルトだけ。設営も撤収も3分以内に終わります。

 樹林帯から急に開ける草原は、鹿たちと登山者の楽園、明神平。元々はゲレンデだったみたいですが、今や近畿を代表する山のテント場。ここでタープ泊する予定でしたが、絶妙に早く着いてしまい水だけ補給して先へ進むことに。明神平でタープ泊、開放感あって最高だろうな…またいつかゆるめの山行で来ようと静かに誓いました。
樹林帯から急に開ける草原は、鹿たちと登山者の楽園、明神平。元々はゲレンデだったみたいですが、今や近畿を代表する山のテント場。ここでタープ泊する予定でしたが、絶妙に早く着いてしまい水だけ補給して先へ進むことに。明神平でタープ泊、開放感あって最高だろうな…またいつかゆるめの山行で来ようと静かに誓いました。 今年は近畿も雪が多かったのか、標高1300m以上の北斜面には所々残雪がありました。ブナの根本は一律に曲がっていて、この木々がまだ細かった時代はさぞ雪が多かったことが伺える。半世紀前の紀伊半島では場所によって一晩で胸の高さまで雪が積もることも珍しくなかったらしい、今では考えられませんね。
今年は近畿も雪が多かったのか、標高1300m以上の北斜面には所々残雪がありました。ブナの根本は一律に曲がっていて、この木々がまだ細かった時代はさぞ雪が多かったことが伺える。半世紀前の紀伊半島では場所によって一晩で胸の高さまで雪が積もることも珍しくなかったらしい、今では考えられませんね。
 この日は暗くなる前に行動を終え、お茶を沸かしてダラダラタイム。チェックした天気予報では降水確率0%で風も弱い、ならばタープは張らずにキルトだけ。設営も撤収も3分以内に終わります。
この日は暗くなる前に行動を終え、お茶を沸かしてダラダラタイム。チェックした天気予報では降水確率0%で風も弱い、ならばタープは張らずにキルトだけ。設営も撤収も3分以内に終わります。
今回のギアで隠れたMVPはMATADOR『ミニポケットブランケット』110cm×70cmのお一人様用レジャーシートで、ハンモックに出入りする際の足場として使用しました。四隅はループ付きで、ペグや枝を刺しておけば夜中に飛ばされる心配もありません。ウェットな場所に座る際や地べたでストレッチする際も活躍。私は以前ストレッチ中にマダニにたかられてから、なるべく敷物の上で寝転ぶようにしています…。タープで寝る時は足元にザックを敷けばグラウンドシートとして全身カバーできますし、ループを利用してレインスカートや極小タープ的な使い方もアリだと思います。こんなマルチプレーヤーでPOWBARよりも小さくて軽い実測38g、お一つあると何かと重宝しますよ。
…3日目以降の山行の様子は<後編>に記していきます。近日公開予定
ここまでご覧いただきありがとうございました。